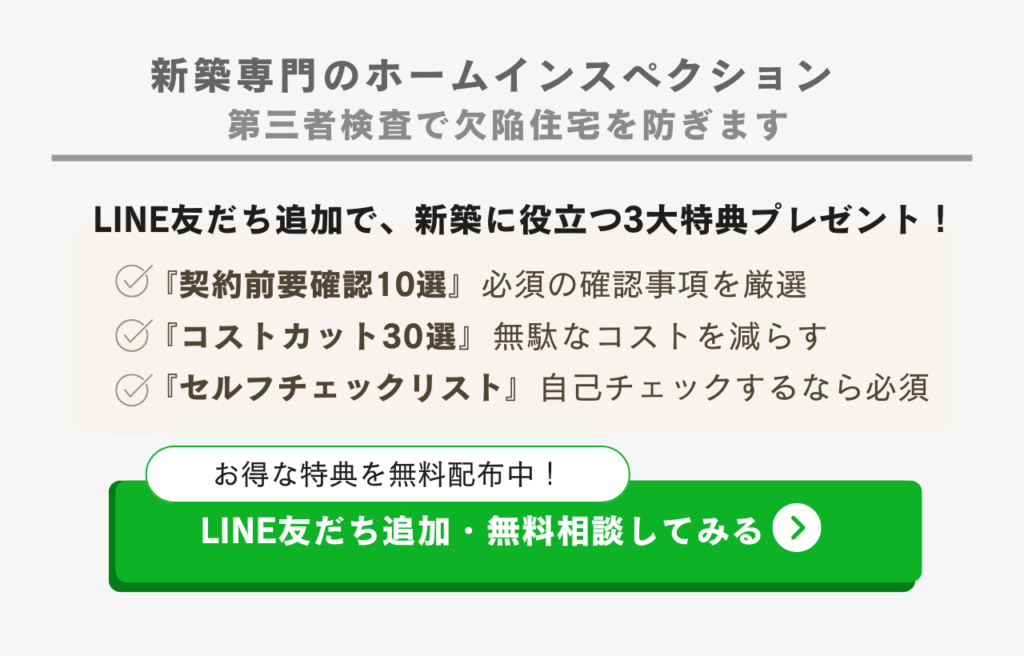長期優良住宅なら安心って思ってたけど…本当に施工までちゃんとしてるの?

制度上の評価と、現場での施工品質は別物です。図面どおりにできているかを確認しましょう!
長期優良住宅は、高い性能基準を満たした住宅ですが、それは設計上の評価に過ぎず、現場施工の精度が伴っていなければ意味を成しません。
本記事では、制度の仕組みと実際の現場とのギャップを整理し、なぜホームインスペクションが最後の確認手段として重要なのかを解説します。
この記事を読むとわかること
- 長期優良住宅の性能評価について
- 長期優良住宅で起きた実際の施工トラブル
- 安心できる家にするためのチェック体制
この記事の監修者
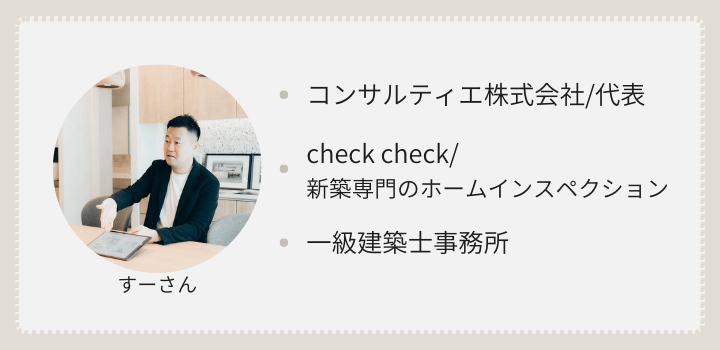
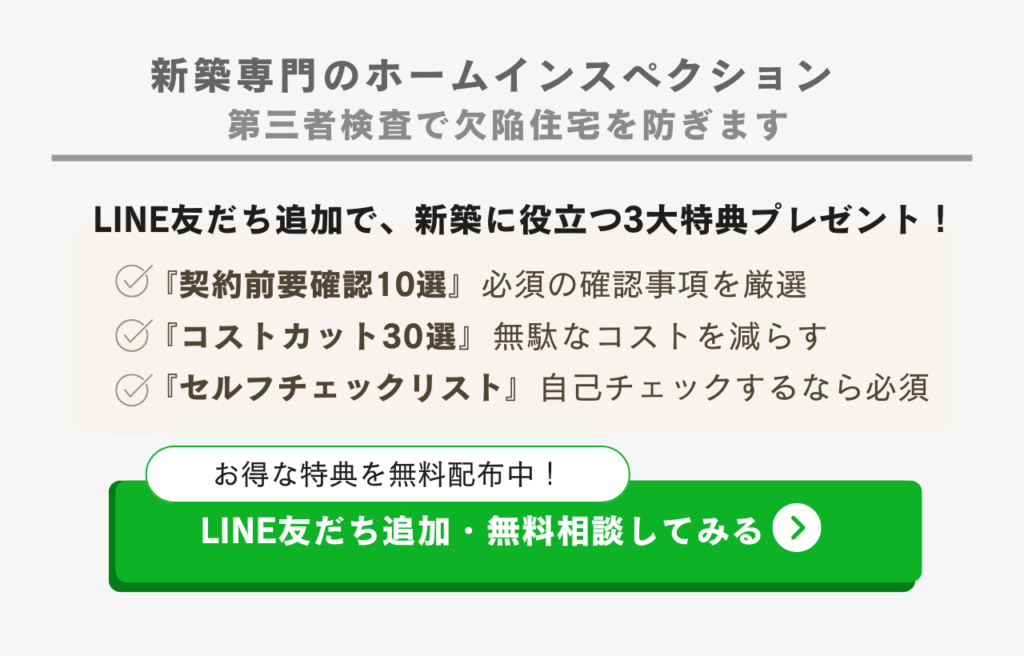
長期優良住宅の性能評価とは何か?

長期優良住宅とは、長期にわたり良い状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。
順番に紹介します。
設計と申請書類を基にした評価
長期優良住宅の認定は、住宅会社が提出する設計図書や申請書類をもとに、性能を評価する制度です。
長期優良住宅の認定とは
- 評価対象は「設計段階の性能」
- 断熱等性能等級・耐震等級などが設計図で判断される
- 実際の施工現場を見ることは制度の対象外
つまり、評価は計画上の性能であり、現場品質の確認はされません。
参考:国土交通省|長期優良住宅のページ
完成品の品質保証ではない点に注意
「認定を取ったから安心」と思っても、現場での施工が雑であれば、設計通りの性能は発揮されません。
長期優良住宅は認定を取っていてもあんしんできない
- 認定は「性能通りにつくること」を前提とした評価
- 施工段階でのズレや省略は評価に反映されない
- 完成品が性能通りかは「別の確認が必要」
性能がある前提で進んでしまうため、誰も施工の精度を見ていない状況が生まれます。
施工精度次第で性能は大きく左右
どんなに高い性能基準でも、実際の現場施工が甘ければ、快適性や安全性にはつながりません。
施工精度次第で左右される性能
- 断熱材がしっかり入っていないと等級は意味がない
- 耐震金物が設置されていなければ強度が落ちる
- 防水シートが破れていれば、長寿命どころではない
設計図の評価ではなく、施工の出来栄えこそが性能の本質です。

制度で「いい家」ができるわけじゃありません。実際に「いい施工」がされてこそ、本当の安心が得られるんです!
現場での施工ミスが性能を台無しにする

長期優良住宅でも、現場で施工ミスが起きると設計上の性能が台無しになります。
一つずつ見ていきましょう。
断熱材の隙間で省エネ等級が意味をなさない
断熱等性能等級を満たすための仕様でも、現場で断熱材が隙間だらけに施工されていれば、冷暖房効率は著しく低下します。
断熱材等性能等級を満たしていても起こった不具合
- 吹付断熱の施工厚みが不均一だった
- グラスウールがズレて一部空洞になっていた
- 小屋裏や床下の断熱が一部未施工だった
設計の数値性能と、実際の室内の快適性は必ずしも一致しません。
金物や構造部の施工ズレが耐震性に影響する
耐震等級3の設計でも、構造金物がずれて取り付けられていたり、規定通りのビスが使われていなければ、本来の強度は発揮できません。
耐震性能に直結する構造部分の施工ミスの事例
- 筋交いの位置のずれ
- 耐震金物の欠落・緩み・違う種類の使用
- 釘の打ち忘れや規定外のピッチで施工
現場での確認がなければ、見えない弱点が完成後も残り続けます。
小さなミスが「優良住宅」の実力を落とす
目立たないミスの積み重ねが、せっかく取得した「長期優良住宅」の実力を半減させてしまうケースもあります。
小さなミスによって影響する住宅の機能性や耐久性
- 換気口の位置がズレて結露やカビの原因
- 結線ミスで一部の設備が作動不良
- 外壁防水の処理漏れで数年後に雨漏りが発生
見えない部分こそ丁寧にが、優良住宅にふさわしい施工品質です。

性能は設計値だけじゃ語れません。現場でのひと手間の差が、家の価値を左右するんです!
長期優良住宅で起きた実際の施工トラブル

ここでは、長期優良住宅で起きた実際の施工トラブルについて紹介します。
順番に見ていきましょう。
認定住宅で断熱材が半分未施工だった事例
断熱材の吹き付けが途中で止まっていたにも関わらず、そのまま壁を閉じてしまい、引き渡し後に一部の部屋が極端に寒くなる問題が発生しました。
認定住宅で断熱材が半分未施工だった事例
- 認定基準は満たしていたが、現場チェックがなかった
- ホームインスペクションで発覚し、是正対応へ
- 気づかず住んでいたら、結露や冷暖房費の無駄につながっていた
図面通りでも、施工されていないという事態は現場では珍しくありません。
耐震金物の未設置で指摘・是正された例
耐震等級3を取得した木造住宅で、柱と梁をつなぐ金物の一部が未施工だった事例もあります。
第三者検査で指摘され、施工会社が是正に応じました。
耐震金物の未設置で指摘・是正された例
- 図面には記載があるのに現場で忘れられていた
- 指摘がなければ、そのまま引き渡されていた
- 家の耐力に直結する“致命的ミス”を未然に防止
設計通りの施工精度は、現場でしか確認できません。
見えない部分での発見されにくい施工不良
完成後は隠れてしまう部分の不備は、発見も是正も難しくなります。
検査がなければ、住み始めてからの違和感やトラブルでしか気づけません。
発見されにくい見えない部分での施工不良
- 壁内の配管がずれて結露が発生
- 防水処理の不備で雨漏りし、床下がカビに
- ボード裏の金物不足で壁の強度が不足
第三者検査は完成してからでは遅い部分を見つける数少ない手段です。

優良の肩書きがあっても、施工が甘ければ意味がありません。チェックする目があるかどうかが、家の真価を決めるんですよ!
あわせて読みたい
ホームインスペクションが果たす現場確認の役割

ホームインスペクションは、図面に描かれた性能が実際の現場施工でも確実に再現されているかを第三者が確認しています。
一つずつ紹介します。
図面通りの施工かを第三者がチェック
ホームインスペクションは、認定制度ではカバーできない施工現場の実態を第三者が確認するための手段です。
第三者による図面どおりの施工かのチェック
- 設計図と実際の施工が一致しているかを現地で確認
- 部材の種類や使用箇所などもチェック対象
- 住宅会社に遠慮せず、中立な立場で指摘
評価通りにつくられているかを裏付けるのが、検査の役割です。
断熱・防水・耐震部材など見えなくなる前に確認
長期優良住宅の中でも特に重要な「断熱性・耐震性・劣化対策」は、施工段階でしか確認できません。
重要部分を施工中にチェックするための検査ポイント
- 断熱材の充填状況、防水シートの貼り方を確認
- 耐震金物の設置場所や種類を現場で照合
- 塞がれる前に、目視と写真で記録
後からは見えない場所こそ、検査の価値が高まります。
設計性能を現実に反映させる役割
せっかく高い性能を設計で確保しても、それを現実に実現するには、施工品質が担保されている必要があります。
ホームインスペクションが果たす役割
- 設計性能と現場品質の橋渡し役として機能
- ミスやズレは早期に是正可能
- 検査記録は「確かに性能通りに施工された証拠」
家の価値は性能スペックではなく、施工の正確さで決まるのです。

ホームインスペクションは制度を活かす道具なんです。設計どおりに作られてこそ、優良住宅の価値が生まれますよ!
あわせて読みたい
長期優良住宅のよくある誤解と制度への過信

長期優良住宅の制度に頼りきりでは、本当の安心は得られません。
制度に対する誤解や過信について紹介します。
「長期優良住宅だから安心」は危険な思い込み
国の認定を受けた住宅という言葉に安心して、現場チェックを怠る人もいますが、それは大きな誤解です。
長期優良住宅の制度の限界
- 認定は図面と仕様書の評価にすぎない
- 施工ミスがあっても、認定が取り消されることはほぼない
- 性能を信じるのではなく、施工精度を見る
制度=完成品の保証ではないことを理解しておきましょう。
住宅会社の検査だけで足りるのか?
多くの住宅会社も社内検査を実施しますが、それが本当に中立で細かい確認になっているかは疑問が残ります。
住宅会社の内部検査の限界
- 担当者自身が自分の現場を検査するケースが多い
- スケジュール優先で検査が省略・簡略化されることも
- 「見たつもり」で済まされるリスクもある
第三者によるダブルチェックこそ、真の安心につながります。
制度に依存しすぎない確認姿勢が重要
「等級が高いから安心」「認定を取ったから大丈夫」と考えるのではなく、自分の家はどうなのかに目を向ける必要があります。
自分自身が施工現場をすべて確認できなくても、第三者にチェックしておらう検査体制を整えるのは大切です。
第三者による施工チェック体制の重要性
- 自分の目で見られなくても、見てもらえる仕組みを持つ
- 長期優良住宅こそ、施工チェックが効果的
- 性能が“机上の数字”で終わらないよう確認体制を整える
制度はあくまで土台。安心は実物で確認することで生まれます。

制度に頼るだけでは守れないこともあります。「うちはどうか?」を見てくれる存在が、今の家づくりには必要ですよ!
あわせて読みたい
本当に安心できる家にするためのチェック体制

住宅の品質確保のためには「設計段階の制度」と「施工段階の第三者チェック」の組み合わせで、安心の家づくりができます。
ここでは、理想のチェック体制について紹介します。
制度 × 第三者チェックのダブル体制が理想
長期優良住宅の制度による「設計評価」と、第三者による「施工確認」を組み合わせることで、初めて本当の意味での安心が得られます。
設計上の性能と現場施工の品質を両方確保するための仕組み
- 設計段階での高性能を確保(制度)
- 施工段階での実現性を確認(第三者)
- 「描いた家が、そのままカタチになる」状態を支える
どちらか一方では不十分です。
「性能と現場」を両方見て初めて信頼できる家になります。
工程ごとの検査で見逃し防止
ホームインスペクションは、1回ではなく複数回の検査で行うことで、重要な工程ごとの見逃しを減らせます。
ホームインスペクションの工程ごとの検査の重要性
- 基礎、上棟、防水、断熱などの節目で検査
- 工程のタイミングに合わせた確認で隠れてしまう前に対応
- 「完成したら見えない部分」こそ高い検査の価値
家づくりは段階ごとに見ておくべきポイントがあります。
住んでからの不安を未然に潰す方法とは?
最終的な目的は、住み始めてからの後悔をなくすことです。
完成後のトラブル・不満・違和感を減らすには、施工段階でのチェックが最も有効です。
施工中に重要部分を検査・確認する意義
- 住んでからの「寒い」「うるさい」「ズレてる」を防げる
- 家族の健康や安全にも直結する部分を事前に確認
- 「ちゃんと作られている」という納得が心の余裕につながる
安心は、完成してからでは得られません。
「つくっている今」が勝負です。

制度と施工の“輪あってこそ、家は本当に安心できるものになりますよ!
長期優良住宅でもホームインスペクションを活用して安心の家づくりをしましょう
長期優良住宅という制度は、あくまで設計性能を評価するものであり、現場でその通りに施工されているかまでは保証されません。
だからこそ、ホームインスペクションで“施工の現実”を確認することが大切です。
設計の理想と、施工の事実。その両方を確かめてこそ、本当に安心できる住まいが実現します。

せっかく長期優良住宅にしたけど、それだけじゃなくて施工が大事なんですね。

設計が良いなら、施工も良くしてこそ完成です。今こそ、目で確かめましょう!
ホームインスペクションや家づくりに関するお悩みがあれば、まずはお気軽にお問い合わせください。